
大学発スタートアップのプラットフォーム運営の現場からRelicへ──“ディープテック事業化”のリアル

時間軸のずれ、人材の不足、資金の谷間——現場で見た大学発スタートアップの壁
大学の研究成果を社会実装につなげる「大学発スタートアップ」。その創出を支える仕組みづくりは、今や国を挙げた重要施策のひとつです。Relicのディープテックイノベーションセンター(DTIC)には、そんな取り組みの初期から現場を歩んできた人材が加わりました。
KSAC(関西スタートアップアカデミア・コアリション)やGTIE(Greater Tokyo Innovation Ecosystem)といった大学発スタートアップ創出のプラットフォーム運営に携わり、研究者と企業の間に立ちながら数々の課題を乗り越えてきた経験を持つ小林。彼が語るのは、制度や理論だけでは語り尽くせない「ディープテック事業化のリアル」です。
Relicへの参画を決めた背景、そしてDTICだからこそ描ける未来とは──。
本記事では、小林のこれまでのキャリアの歩みと、大学発スタートアップ支援の現場で直面したリアルな課題を紹介します。また、彼がRelic DTICに惹かれた理由、金子所長との出会いがもたらした衝撃、そしてこれから挑戦したい未来像についても語ってもらいました。大学・研究機関や金融業界で支援に携わる方はもちろん、ディープテック領域で挑戦したい方にとっても、キャリアのヒントとなる内容です。
登場人物プロフィール
小林輝樹
2001年に京都銀行へ入行し、約20年にわたり法人・個人営業を担当。その後、京都大学への出向を機に大学発スタートアップ支援の世界へ。研究成果の事業化支援や産学連携の仕組みづくりに携わり、KSACやGTIEといった国主導のプラットフォーム運営を経験。2025年よりRelicに参画し、ディープテックイノベーションセンター(DTIC)にて大学発スタートアップの事業化支援を担う。
銀行員から大学発スタートアップ支援へ——「社会課題を解決できる技術」との出会い
小林は2001年に京都銀行へ入行し、約20年にわたって大企業から個人事業主、資産運用を行う個人まで幅広い顧客を対象に営業を担当しました。
転機は2018年、京都大学への出向です。研究成果を社会に実装する仕組みづくりに携わることになり、初めて「大学発スタートアップ」という領域に触れました。
「大学の研究成果には、一つ形になれば必ず社会課題を解決できる力があると感じました。自分自身が技術を持っているわけではありませんが、研究者を支援することで間接的に社会課題の解決に貢献できる。それが大きな魅力でした。」
銀行員として培ってきた「社内外のリソースを組み合わせて顧客課題を解決する姿勢」は、研究者と企業をつなぐ際にも活きました。しかし一方で、企業が求めるスピード感と研究者が重視する研究の時間軸は真逆であり、両者を理解して橋渡しできる人材が不足していることを痛感したといいます。
KSACでの挑戦——国策の最前線から関西を底上げする
その後、小林は京都銀行に帰任しましたが、大学の研究成果を社会に実装する仕事を続けたいという思いが抑えられず、転職により京都大学に戻ることを選びました。京都大学に戻ってからは、関西一円の大学が連携するプラットフォーム「KSAC」の運営を担当しました。
この取り組みは、国が2020年に打ち出した「スタートアップ・エコシステム拠点都市」施策(いわゆるグローバル拠点都市)の採択をきっかけに生まれたものです。京阪神エリアは「関西イノベーション・エコシステム拠点都市」として指定され、世界に通用する大学発スタートアップを創出することが国からも強く期待されていました。KSACはその受け皿として形成された、関西から持続的にスタートアップを生み出すことを目指した大規模なプロジェクトでした。
しかし、当時のKSACはまだ立ち上がったばかり。京都大学や大阪大学といった一部の大学では仕組みが出来始めていたものの、多くの大学はスタートアップ支援の経験すらなく、体制や文化には大きな温度差がありました。ある大学では「スタートアップとは何か」を理解してもらうところから始めなければならず、別の大学では研究成果は豊富でも「起業は自分ごとではない」と躊躇する研究者の背中を押すのに苦心することも。

小林:「主要大学はすでに仕組みを作り始めていましたが、整備が追いついていない大学も多くありました。プラットフォームとしては全方位的に支援を提供し、関西圏全体を一段上のレベルに引き上げなければならない。その難しさを常に感じていました。」
膨大な予算を預かる責任も重くのしかかりました。国の期待は「関西から世界に通用するスタートアップを生み出すこと」。しかし大学ごとに状況は異なり、一律の施策では機能しません。小林は事務局や他大学の担当者と議論を重ね、成熟度に応じて個別支援と全体施策を組み合わせる「多層的な支援策」を形にしていきました。時には「全体最適」を優先するあまり不満が出ることもありましたが、それでも「関西全体を底上げする」という目標をぶらさずに進めていったのです。
こうした奮闘の中から、KSACではスタートアップ創出を目指す研究者を支援する研究開発助成制度(KSAC-GAPファンド)を整備し、すでに80件以上のプロジェクトの支援を開始しています。さらに、KSACの主幹機関を務める京都大学からは、「エネコートテクノロジーズ」「京都フュージョニアリング」「リージョナルフィッシュ」といった世界的に注目される大学発スタートアップも誕生しました。ペロブスカイト太陽電池や核融合、ゲノム編集といった先端技術が事業化される過程を間近で支えた経験は、小林にとって大きな財産となりました。こうしたスタートアップに続く将来有望なプロジェクトを創出する仕組みづくりの現場で得た知見や感覚も、彼のキャリアの揺るぎない土台となっています。
GTIEで芽生えた「成し遂げたいこと」
さらに小林は東京科学大学に移り、首都圏の大学が連携する「GTIE」の運営にも携わります。関西とは異なり、首都圏の大学は資金や仕組みが比較的整っており、エコシステム全体を俯瞰しながら支援できるというやりがいもありました。
しかし一方で、制度や仕組みの運営に比重が置かれることで、研究者や個々の技術シーズにじっくり寄り添う機会は限られてしまう。その現実を目の当たりにしながら、小林の中では「制度設計や運営だけで終わりたくない」「一つひとつの研究成果を事業として社会に届けたい」という想いが日に日に強まっていきました。
「GTIEでの経験は貴重でしたが、やればやるほど“自分が本当にやりたいこと”が鮮明になったんです。制度を作ることも必要だけど、それ以上に目の前の研究者や技術に伴走し、事業化まで責任を持って支えたい。そんな気持ちが抑えられなくなっていきました。」
こうして小林のキャリア志向は、制度運営の枠を超えて、より現場に近い事業化支援へと大きくシフトしていったのです。
ディープテック事業化の本質的な課題
小林はこれまでの経験を振り返りながら、現場で強く感じてきた課題をこう語ります。

「まず大きいのは、研究者と企業の時間軸の違いです。企業は『来月には解決策が欲しい』と迫る一方で、研究者は『数年かけてでも確実な成果を出したい』と考える。この溝には何度も直面しました。僕自身、双方の理解を得るために何時間も調整に走ったことがありますが、やっぱり大学と企業、どちらの言語も理解して橋渡しできる人材がいなければすぐに行き違いが生まれてしまうんです。」
「次に、人材不足です。研究者は技術には長けていても事業化の経験は乏しい。逆に事業の経験が豊富な人は技術を深く理解していない。CEO人材、投資家と交渉できる人材、研究シーズを発掘・見極められる人材……必要な人はたくさんいるのに、現場では常に『誰もいない』という状況が続いていました。僕自身、プロジェクトを進めたくても任せられる人がいなくて立ち止まった経験は何度もあります。」
「そして何より切実なのが資金の断絶です。大学発スタートアップは“アーリーのさらに前段階”にあたるので、まだ製品やサービスの形がない。だから民間VCは投資をためらってしまう。結果として補助金頼みになり、制度が終われば取り組みも途切れてしまう。大学発スタートアップの一番の課題は“谷間の資金”です。目の前で優れた研究が資金不足で止まってしまう場面を何度も見てきました。論文は評価されても社会実装には至らず消えていく。ここを埋める仕組みがなければ、多くの技術は日の目を見ないまま終わってしまうんです。」
Relicとの出会い——「頭の中の解決策が言語化されていた」
小林がRelicに惹かれるきっかけは、DTIC所長・金子佳市との出会いでした。
「金子さんが大学向けに説明していた支援内容が、僕がずっとやりたいと思っていながら制度や立場の制約で実現できなかったこととほぼ一致していたんです。自分の頭の中にあった解決策が、明確に言語化されていて正直衝撃を受けました。」
大学の事情を深く理解したうえで、GAPファンド申請の支援から事業化までを一貫して支える具体性と実行力。これまで接してきた「表面的な提案」に終始する民間機関とは明らかに異なっていました。
「ここなら本当に事業を形にできる」と確信し、小林はRelic DTICへの参画を決意しました。

Relic DTICで描く未来
現在、小林はKSACに参画する大学を中心に支援を行っています。今後はさらに対象を広げ、エコシステム全体を支える取り組みに挑戦したいと語ります。
「Relicには、戦略から実行までトータルで支援できる人材が揃っています。誰かに相談すれば必ず応えてくれる。そんな総合力が強みです。社会を変える技術を事業に変え、DTICから生まれるスタートアップで社会を変革していきたいと思います。」
Relicの強みは、単に知見やノウハウを持っているだけではありません。全国350名を超える多様なバックグラウンドのメンバーが在籍し、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブといったあらゆる領域をカバーできる点にあります。新規事業の構想段階から、プロトタイピング、資金調達、広報・ブランディングまでワンストップで伴走できる体制は、他にはないRelicならではの魅力です。
ここには明確に、「Relicの組織力・実行力・総合力」という三つの強みがあります。第一に、350名規模の多彩な人材が結集する“組織力”。第二に、机上の戦略に終わらず事業を具現化できる“実行力”。そして第三に、ヒト・モノ・カネすべてを動員し事業化をトータルで支援できる“総合力”です。この三位一体の力が、ディープテック領域で「最後までやり切れる支援」を可能にしています。
小林:「Relicには“ここまでやってくれるんだ”と感じる総合力があります。制度や立場の制約でできなかったことも、この環境なら実現できると確信しています。」
さらにRelicには、異なる専門性を持つ仲間と切磋琢磨しながら働ける環境があります。起業経験者や大企業での新規事業責任者、研究者出身のメンバーなど、多様なバックグラウンドを持つ仲間と協働することで、新しい視点や実践的な学びを日々得られるのです。小林は「この環境なら、長年の課題だった“谷間の資金”や“人材不足”にも解決策を見出せる」と期待を寄せています。
採用情報
Relicのディープテックイノベーションセンター(DTIC)では、技術を事業化し社会を変革する仲間を募集しています。
小林は、これから挑戦したい未来をこう語ります。
「社会を変える技術を、事業という形に変えていく。DTIC発スタートアップで社会を変革しよう。」
この言葉の通り、Relicには多様な専門性を持つ仲間とともに研究成果を事業へと昇華させる仕組みと実行力があります。ここでなら、これまで埋もれていた技術を本当に社会実装へと導くことができます。
未来を動かす挑戦に、あなたも加わってみませんか。


社員の声

大学発スタートアップのプラットフォーム運営の現場からRelicへ──“ディープテック事業化”のリアル
ディープテックイノベーションセンター

地方創生の鍵は“挑戦が続く仕組み”──Relicが取り組む、新規事業支援と地域イノベーションの現在地
執行役員 | グローカルイノベーション事業部長
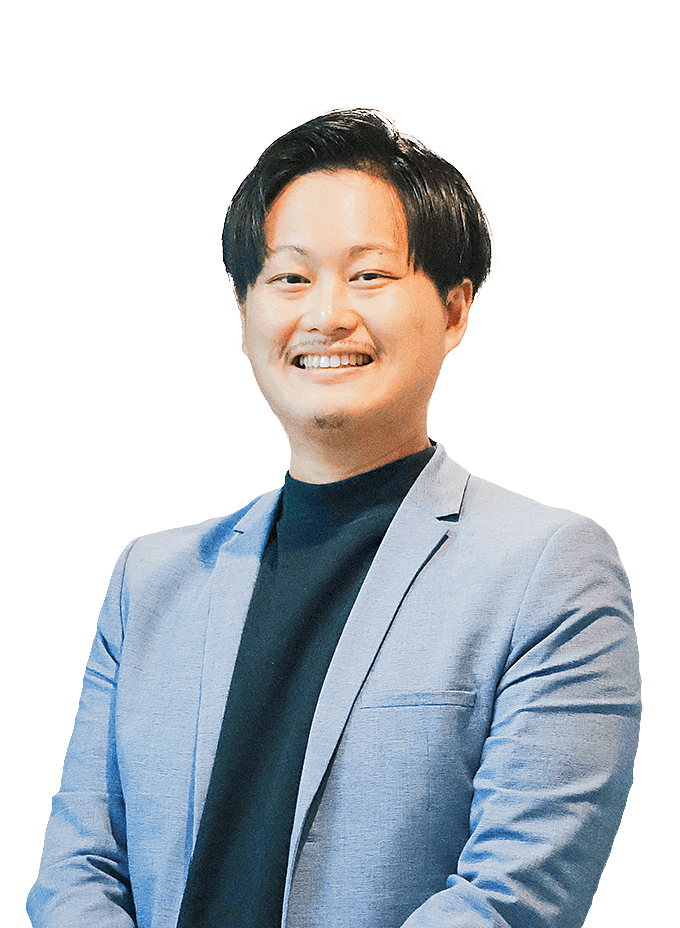
ディープテック×新規事業開発で最前線へ。ディープテックイノベーションセンター所長 金子佳市のキャリア
ディープテックイノベーションセンター
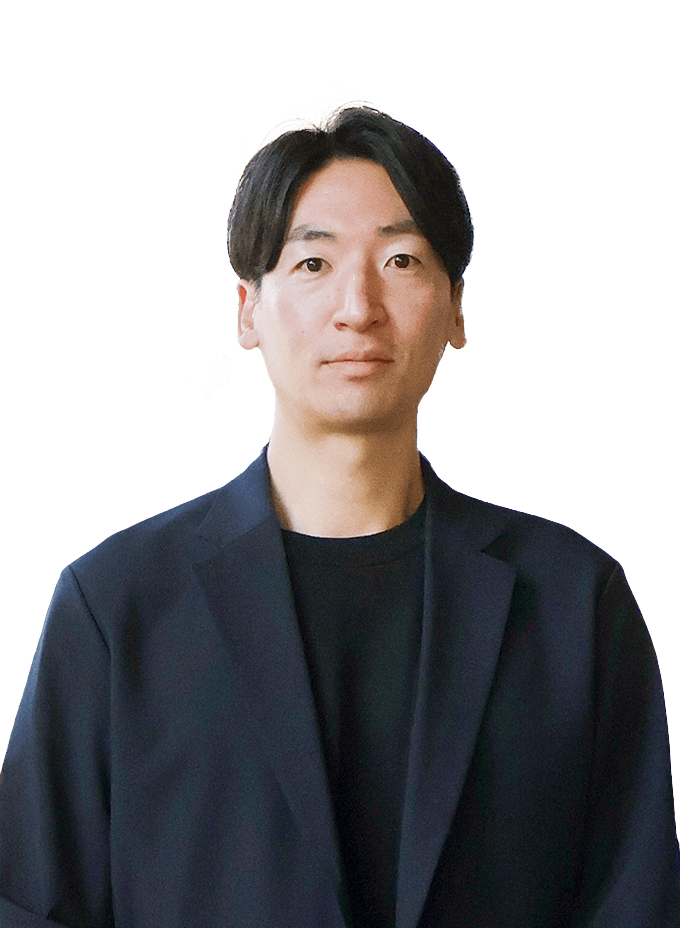
【COO兼CMOインタビュー】新規事業の成功を導くグローススペシャリストの育成と営業人材の飛躍
取締役COO 兼 CMO

【CTOインタビュー・後編】新規事業立ち上げに不可欠な「不確実耐性」が身につく、Relicのエンジニア
大庭亮 取締役CTO l Co-Founder プロダクトイノベーション事業本部長
