【後編】Game Changer Catapultを通じて受け継がれる 「松下電器のDNA」と「アップデートされるパナソニックのDNA」
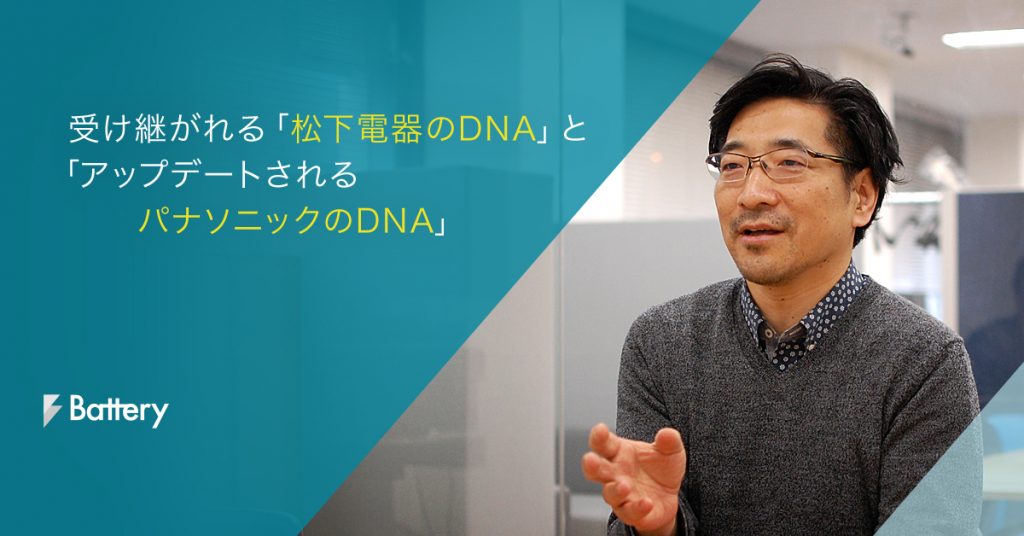
パナソニック株式会社 アプライアンス社(以下パナソニック)における新規事業開発プログラム「Game Changer Catapult(以下GCカタパルト)」、その代表を務めるパナソニック アプライアンス社 Game Changer Catapult代表 深田昌則(ふかた まさのり)氏に前編ではGCカタパルトが未来のカデンを生み出す仕組みについて語っていただきました。
後編の今回は、GCカタパルトを通じて受け継がれている創業者松下幸之助氏の想いとパナソニック社内の組織や人にどのような変化や兆しが生まれているのか語っていただきます。
(Battery編集部)
GCカタパルトという取り組みは、パナソニック社にどのような変化を生み出しましたか?
(深田氏)
社内組織の変革です。GCカタパルトを創設し活動し始めてから、社内で様々な部門に変革やイノベーションに取り組むグループが生まれてきたことも、お互いに触発し合いながら進めてきた一連の流れと考えています。
例えば、デジタル時代に対応する“もう1つのパナソニック”として米国シリコンバレーに設立した「Panasonic β」や、パナソニック内の先行開発に特化して活動するデザインスタジオとして設立された「FUTURE LIFE FACTORY」、常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが100年先の未来を生み出すという考えで設立された本社部門の社外活動「100BANCH」などもその例ではないでしょうか。お互いにコンタクトを取りノウハウや知見について意見や情報交換をしながら進めています。
そして2017年には我々が「FUTURE LIFE FACTORY」と「100BANCH」を引き連れ、SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)というアメリカのイベントで出展を実施しました。ただ「Panasonic β」や「FUTURE LIFE FACTORY」「100BANCH」はどちらかというと本社・イノベーション部門やデザイン本部に属していて、我々はビジネスに近いアプライアンス社という事業カンパニーに属しており立ち位置が異なるので、緩い形での連携となっています。
「新規事業企画部」のような部署名ではなく、「Game Changer Catapult」のような独自の名前をつけるという組織ブランディングは、我々がまず挑戦し、流れを作り出すことができたと思っています。
(Battery編集部)
様々な社内部門との連携などのお話を伺うと、GCカタパルトは社内にもいい影響を生み出している取り組みだということがわかりました。GCカタパルトの取り組みを始める前は、このようなイノベーションに関連する部門が横断的に情報交換できる機会や交流はあまりなかったのでしょうか?
(深田氏)
ちょうどここ3年くらいで各部門が横断的に情報交換できる機会を持ったり、交流をしたりすることが社内でも当たり前になりました。それまでは縦割り型の組織に縛られ、部門を超えて会話することはあまりありませんでした。社名がパナソニックに代わる前の話をしますと、松下電器と松下電工はもともと別会社で、それぞれが同じ「ナショナル」ブランドで競合製品を出していたりしていました。
ご存知の通り、松下幸之助は初期の事業成長期に多角化戦略を取り、事業部制を生み出しました。事業部の中で開発、製造、販売を行う自主独立経営です。この事業部制を取るメリットは、全ての判断を松下幸之助に仰ぐ必要なく各事業部判断で決定ができる点です。
いわゆる権限移譲ですね。但しその反面、各事業部が壁を作りながら、重複した商品を発売するということも起こっていました。それは当時、創業者の松下幸之助が意識して社内で多様性を維持する戦略として実施していたのだと思います。
また、松下幸之助は会社が出来て15年くらいの頃に、松下電器は何のために立ち上げた会社なのかというミッションを発表しました。その際に、従業員の皆が感動して我先にステージに立って決意を発表するハプニングも有りました。今でもベンチャー企業でよくありますよね。
お金儲けのためにやっているのではく、社会を創るために事業を創り運営している。それが今のパナソニックにも受け継がれていて、現在のビジョン、ミッション、バリューに結びついています。
それでも当時、今のパナソニックと同じことが創業当時にも起きていたのではないかと思っています。新しいベンチャー企業が生まれて、当時の大手企業からエレクトロニクスという新しい事業に夢のある若者がいましたが、それでもベンチャー企業であるがゆえに採用には苦労したようです。
そのため、松下幸之助は夢を持って入社してきてくれた若者が成長できるように一生懸命考えてメッセージを発信していました。例えば「松下電器が将来いかに大を成すとも、一商人たるの本分は忘れず」という言葉があり、それが今に生きています。GCカタパルトの取り組みをしていると、GCカタパルトの参加者や他部署からもこの考え方を思い出しましたと言われることもよくあります。
私たちがGCカタパルトで教えているのは「このメンバー自身、自分たちで全部事業を創るんですよ」ということです。つまり、「自分が商売をやるということを考えないとダメですよ」ということを伝えています。こういったことが先程の「松下電器が将来いかに大を成すとも一商人たるの本分は忘れず」という考え方に通じていると感じ取ってもらっているのかもしれないですね。
(Battery編集部)
GCカタパルトに参加されたカタパリストの方々が卒業後に起こした変化についてはいかがでしょうか?
(深田氏)
そうですね、GCカタパルトで初めて新規事業やイノベーションの世界を知ったことがきっかけで、卒業後もチャレンジをし続けているカタパリストが増えています。例えばGCカタパルト2期生の方でGCカタパルト参加後に「始動」という経済産業省のプログラムに応募して通過しシリコンバレー派遣組になったケースもあります。
また、GCカタパルトの活動を通じてUXの重要性を学び、GCカタパルト卒業後に自部署内にUX課を作ったという事例もありました。さらに、アメリカ日本居を置くベンチャーキャピタルScrum Venturesとパナソニックが新規事業の創出促進を目的として立ち上げた株式会社BeeEdgeに、GCカタパルトで生み出した事業テーマを移管して法人化したケースもあります。
そもそも移管された1社目のミツバチプロダクツはカタパリスト1期生が別のアイデアで再チャレンジし株式会社BeeEdgeに提案して事業化したものです。シニアの課題を解決するために作り上げたやわらか食カデン「DeliSofter(デリソフター)」はGCカタパルトの中から誕生した事業アイデアで、カタパリストが現在BeeEdgeの傘下にギフモ株式会社を設立しています。
(Battery編集部)
参加されたカタパリストの方々がGCカタパルト後も社内外を巻き込んで挑戦を続けておられ、素晴らしい意義のある取り組みだと思います。
(インタビューを終えて)
GCカタパルトから「DeliSofter(デリソフター)」や「OniRobot(オニロボ)」といった未来のカデンが生まれ続けている背景には、「新規事業へのパッションとモチベーションを持ち続けるカタパリスト」と「カタパリストを支える社内メンター」の存在がありました。
そして部門を横断した交流の機会が生まれるなど、GCカタパルトを通じて組織や人にポジティブな変化が起きていました。「新規事業開発プログラムを実施しているが思うような成果が出ていない」企業にとって、このGCカタパルトの取り組みが一筋の光になるのではないでしょうか。
Facebookページから
最新情報をお届け
記事のアップデート情報や新規情報はFacebookページで随時配信されております。
気になる方は「いいね!」をお願いいたします。
新規事業・イノベーションガイドブック

4,000社、20,000の事業開発で得た新規事業立ち上げのノウハウを一部無料公開。
<本資料の主な解説事項>なぜ今、新規事業やイノベーションが必要なのか?
新規事業開発は、なぜうまくいかないのか















