新規事業の成功確率を上げる体制構築と仕組み作りとは
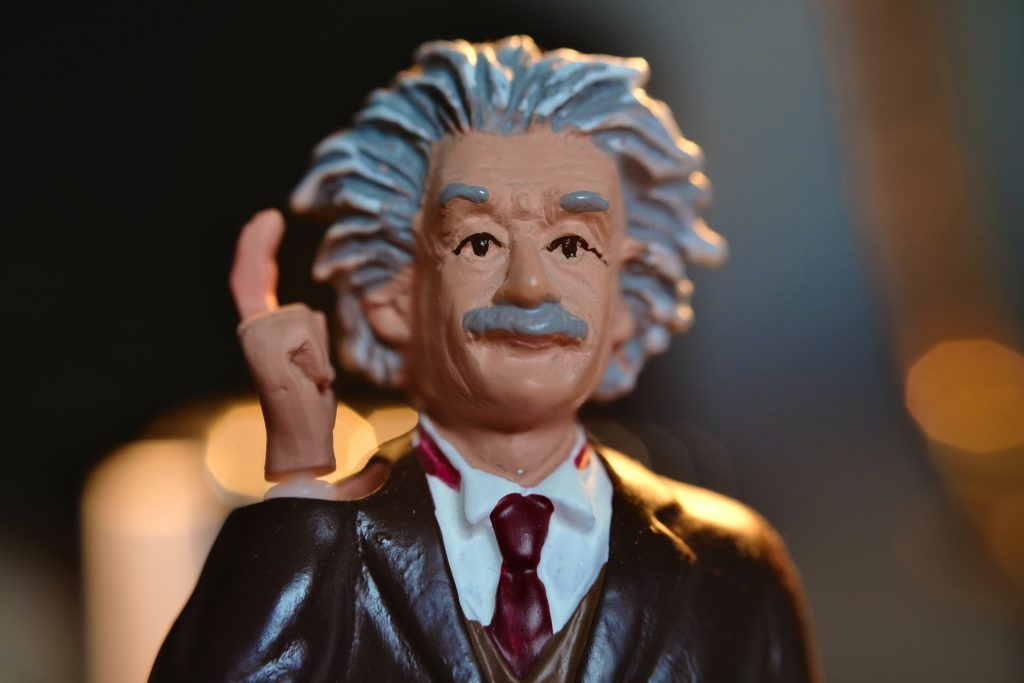
新規事業は、多くのチャレンジが重要です。なぜなら、ほとんどの事業はうまくいかないためです。
うまくいかない原因としては、アイデアの事業性や実現性の低さなどが挙げられますが、そもそも事業を生み出し、推進するアプローチ(体制/仕組み)に問題がある場合も多く見受けられます。そして、その問題の原因を解消するには、新規事業開発の目的や時間軸、主要なアセットの所在を定義することが重要です。
今回は、適切なアプローチを選択するために、どのような観点・順番で検討するかについてご紹介します。
Contents
アプローチを決める観点と最適な推進体制
アプローチを検討する上で目を向けるべき観点は大きく分けて3つあります。
1. 新規事業開発の目的 / 意義 (事業観点 / 組織観点)
2. キーアセットの所在 (自社 / 他社)
3. 課題やニーズの不確実性と時間軸 (高い・潜在的・長期 / 低い・顕在的・短期)
新規事業開発の目的 / 意義(上表の縦軸)
まずは「新規事業開発の目的や意義」に目を向けます。
事業成果のみを追究するとは、たとえば、元からある既存事業で2つの収益の柱があったとき、さらに3つ目の柱を立てて3年後までに100億円の事業を作りたいというような“事業的な成果”を一番重視する場合が該当します。
事業成果に加えて組織/人材観点を重視するパターンもあります。例えば新規事業開発のプロセスに適した人材を育てていきたい、新たなチャレンジをしたいといった声が社内から上がるようにしたいなど「人材育成」や「企業風土の醸成」に向けた組織的な観点を重視する場合が該当します。
例えば、経営層と新規事業推進部門の間で目的や意義の認識が異なっていると、成果が出る前に活動が打ち切りになってしまうという可能性もあります。
キーアセットの所在(上表の横軸上部)
次に、「新規事業開発を進めていく上で必要となるキーアセット(事業開発/運営上、重要な資産や資源)がどこにあるのか」に目を向けます。
クローズドイノベーション
キーアセットが自社にあるとは、新規事業の競争優位性の源泉になり得るアセットが自社にあり、それを活用・拡張していくことで事業創出が可能な場合が該当します。
オープンイノベーション
キーアセットが他社にあるとは、自社のアセットは当然使いながらも、社外のベンチャー企業や大企業など他社のアセットを取り込み、うまく組み合わせることで優位性や独自性を生み、新規事業を創出していく場合が該当します。
課題やニーズの不確実性と時間軸(上表の横軸下部)
さらに、「新規事業によって解決する課題やニーズの種類」に目を向けます。
「課題やニーズの不確実性が高い」もしくは「時間軸が長期的」とは、まだ潜在的な顧客ニーズを狙って中長期で市場や顧客を啓蒙し、成果を出していく必要のある事業の場合が該当します。
「課題やニーズの不確実性が低い」もしくは「時間軸が短期的」とは、すでに顕在化している顧客ニーズを狙って短期間で成果を出しやすい類の事業の場合が該当します。
この観点の検討が漏れてしまうと、やはり経営層と新規事業推進者の間で認識が異なってしまい、期待した時間軸で事業化できない、もしくは十分な数の事業を生み出せない可能性があります。
まとめ
今回ご紹介したアプローチはどれか一つを選ばなければならないわけではありません。
新規事業開発プログラムで社内の風土醸成をしていきながら、一方でM&Aで社外のベンチャーを取り込んで事業的な成果につなげるという手法もあり、特定のアプローチだけ一点突破で進めるという極端な考え方だけではなく、例えば3つのアプローチに5:3:2の割合でそれぞれに適切な人材とお金を投資して、ポートフォリオを作り、事業の種を生み出していくというような推進の方法もあります。
具体的な新規事業案を丁寧に検討・検証していくことももちろん大切ですが、今回ご紹介したアプローチの検討をはじめとした、成功確率を構造的に上げる取り組みもご検討いただければ幸いです。
Facebookページから
最新情報をお届け
記事のアップデート情報や新規情報はFacebookページで随時配信されております。
気になる方は「いいね!」をお願いいたします。
新規事業・イノベーションガイドブック

4,000社、20,000の事業開発で得た新規事業立ち上げのノウハウを一部無料公開。
<本資料の主な解説事項>なぜ今、新規事業やイノベーションが必要なのか?
新規事業開発は、なぜうまくいかないのか















